春から初夏にかけて、店先に並び始める「そら豆」。
ふっくらとした食感と、ほんのりやさしい甘み。
見つけると、あぁ、今年もこの季節が来たなぁって、なんだか嬉しくなります。
でも、そら豆って、ただ「おいしい」だけじゃないんですよね。
実はその名前には、昔からの深い由来があり、縁起にまつわる意味もあるんです。
今回は、そんなそら豆の名前の由来や語源、別名、原産国、そして縁起の良し悪しについて、私なりにたっぷりご紹介していきたいと思います!
そら豆の名前の由来、語源は?
そら豆って、空に向かってぐんぐん伸びていくんですよね。
だから「そら豆」って名前がついたんだって。
その話を聞いたとき、なんだかすごく納得しちゃいました。
空に向かってまっすぐに伸びる姿って、元気いっぱいで可愛くて、見てるだけでパワーをもらえそう。
それに、そら豆は「蚕豆(さんとう)」って漢字でも書くんですよね。
これもまた素敵な由来で、さやの形が蚕に似ていることとか、蚕が繭を作る季節にそら豆がちょうどおいしくなるからって言われているんだとか。
昔の人たちは、自然の巡りを本当に大事にしていたんだなぁって、そんなところにも感じます。
お店に並ぶそら豆は、黄緑色のフレッシュなものが多くて、思わず手に取りたくなる。
やっぱり、塩ゆでがいちばんシンプルでいちばんおいしい!
ふっくらとした甘みを頬張ると、春から初夏にかけての、あの爽やかな空気まで感じるような気がするんです。
完熟したそら豆は、乾燥させて保存されることが多くて、煮豆やおたふく豆に。
こちらはまた、コクのある甘みがあって、季節が変わってもそら豆を楽しめるのがうれしいんですよね。
移り変わる季節と一緒に、そら豆の表情まで変わっていくみたいで、なんだかほっとします。
そら豆には別名はある?
そら豆に「夏豆」っていう別名があるって、初めて知った!という方もきっといらっしゃると思います。
でも実は、それだけじゃないんです。
そら豆には、びっくりするくらいたくさんの別名があるんですよ。
なんだか、そら豆って不思議な存在ですよね。
たとえば、大和豆(やまとまめ)、唐豆(からまめ)、がん豆、四月豆、五月豆、冬豆、雪割豆、雁豆(がんまめ)、胡豆(こず)、ノラマメ。
さらに、中国では辛味噌でおなじみの「豆板醤(とうばんじゃん)」の原料として、「豆板(とうばん)」とも呼ばれています。
面白いのは、地域によって呼び方が違うこと。
奈良では「大和豆」、四国では「唐豆」、静岡では「がん豆」って呼ばれていたりします。
地元によって、そら豆との付き合い方も少しずつ違うんだなぁって感じますね。
それに、別名には季節を表すものもあるんです。
「四月豆」は4月ごろから収穫が始まるから、「五月豆」は5月がピークだから。
「冬豆」は、冬に種をまくから。
そして、「雪割豆」は、秋に植えて、雪が解けたあとに収穫されることから。
千葉県あたりでよく使われる呼び方みたいですよ。
とはいえ、やっぱり一番親しまれているのは「そら豆」という名前。
空に向かって実をつけるから「空豆(そらまめ)」なんて説もあるけど、実は「田んぼの畔(あぜ)道に植えられていたから、野良豆(のらまめ)って呼ばれていたのが変化した」っていう説もあるんだとか。
昔から、人と自然の中で育まれてきたそら豆。
呼び名がたくさんあるのも、たくさんの人たちに愛されてきた証なのかもしれませんね。
そら豆の原産国はどこ?
そら豆の原産地や祖先については、実ははっきりとはわかっていません。
ただ、北アフリカや南西アジアあたりが起源と考えられています。
日本には、奈良時代にインドの僧・仙那(せんな)によって、中国から伝えられたという説もあります。
ただし、古い文献にそら豆がはっきりと登場するのは、もう少し後のこと。
江戸時代、林羅山(はやし らざん)が書いた『多識篇(たしきへん)』に、「蚕豆(さんとう)」という名前で記録されています。
この「蚕豆」という呼び方は、蚕(かいこ)が繭を作る季節においしくなる豆という意味からきたといわれています。
また、若いそら豆のさやが上向き(空に向かって)育つことから、「空豆」とも書かれるようになったんですね。
古くから、季節の流れや自然の動きを感じながら、大切に食べられてきたそら豆。
その由来を知ると、ますます愛着が湧いてきますね。
そら豆は縁起がいい?悪い?
ソラマメは、空をめざしてまっすぐ実をつける豆。
未来に向かって進んでいく力を、そっと応援してくれるような存在です。
「豆に生きる」「豆々しく働く」といった言葉にあやかって、健康や勤勉さを願う意味でも、昔から豆が親しまれてきました。
豆料理には、長生きしたい、元気でいたいという人々のあたたかい思いが込められているんですね。
まとめ
そら豆って、ただおいしいだけじゃなくて、名前の由来や歴史、たくさんの別名、そして縁起にまつわる話まで、知れば知るほど奥深い存在ですよね。
空に向かってぐんぐん伸びるそら豆は、未来に向かって進む力を象徴していて、
「豆に生きる」「豆々しく働く」といった言葉に込められたように、健康や勤勉さ、長寿への願いとも結びついています。
春から初夏にかけての旬の時期には、ぜひそら豆を食卓に取り入れてみてください。
自然の恵みと一緒に、未来に向かう元気なパワーも、きっと取り込めるはずです。
最後まで読んで頂きありがとうございます。


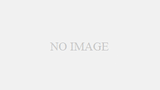
コメント